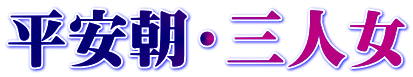  光源氏の困惑と怒り。息子の親友の子を生んだ妻・女三宮は、死にたい、と泣くが…。 男と女にまつわる話は、古今東西、尽きることが無い。いつの時代も、どんな環境の中でも、変わりなく論じられ、それが脚色されて巷間に広まる。古典の多くや、和歌などは色恋沙汰無しには成り立たない時代そのものを映し出している。平安時代は世の中が必ずしも平安であったわけでは無いが、現代のタガの外れた世界に生きる人々に取っても、仰天の倫理感がしっかりと根を下ろしていたようだ。 三人女と言うのは清少納言、紫式部、和泉式部の才女。ご存じ枕草紙、源氏物語、冴え渡る和漢数々…。ゆっくり読んだり、飛ばし読みだったりだが、ジジ流の解釈を待つまでもなく、面白い。博学の先生方や古典マニアにはそれこそ「コテン・コテンに」おしかりを受けるだろうが、そこはジジ流解釈に免じて寛容に願うところ。 清少納言の裾捲り 恋に生きる和歌の名手 名作・源氏物語を書いた女 廊下が騒がしい。まだ朝も早いのに…。清少納言がそう思って立ち上がったとき、駆けてくる足音が聞こえ、襖が乱暴に開かれた。黒ずくめ、抜き身を持った男が目を血ばしらせて部屋へと踏み込んだ。 「小僧。逃さんぞ!」 清少納言は僧の衣だった。このままではやられる。尼だと分からせないといけない。 「わたしゃ、女じゃ!」 咄嗟のことだった。清少納言は衣の裾をつかむと“ガバッ”と肩までたくし上げた。前は丸見え。抜き身の賊は仰天。唖然として動きを止めた。当時は今のような下着は無い。せいぜい布を巻き付けたお腰、くらいのものだ。丸見え。 「女を斬るか!」 清少納言の一喝に賊は叫び返した。 「失せろ」 賊は声を挙げたが、部屋へ飛び込んだのは賊の方で、失せるのは自分なのを忘れた。  女装なら襲われもしまいに… このとき清少納言は兄の清監、致信の屋敷に居た。兄二人は時の権力者藤原道長に仕える藤原保昌の郎党で、貴族社会の隠れた権力争い、裏社会で暗躍する先兵としての行動を請け負ったりもしていた。このときは道長のライバルでもある源頼親の配下を殺傷した遺恨返しで襲撃されたという。清少納言に取ってはあずかり知らぬことではあるが、同じ屋敷に居て僧の姿だったので、危うく巻き添えを食らうところだった。兄二人はこのとき命を取られた。 頼親は淸原致信(清少納言の兄)の殺害のため、1017年3月に八人の騎馬武者、数十人の私兵を率いて淸原致信の邸宅を襲った。酒呑童子退治などで知られる頼光の弟、源頼親の率いる四天王、渡辺綱らも含まれていたとする言い伝えもあるので、この時代では”トップクラス”の暗殺集団同士の戦いだったと推測できる。清少納言の“女をさらけ出した気迫”のためか、部屋へ侵入した男は、僧衣一枚の女を斬るわけには行かなかったのか-。いずれにしても九死に一生、と言う裾まくりではあった。 ちょっと覗き見  この餓鬼を殴れ 清少納言は一条天皇の中宮、定子(ていし)に仕えた。中宮は妃の中でも最高位で、藤原道隆(みちたか)の娘だった。当時の貴族社会では娘が天皇の寵愛を受け、子を成すことを願っていた。大勢力を持つ藤原家も例外ではなく、貴族の娘で才能のある者を娘の周囲に集めた。 春は曙…。夏は夜…。秋は夕暮れ…、冬は早朝…。王朝の四季絵巻を書き始めから見事に描写する清少納言は、第二章に入ると、奔放な男女関係の無礼講を描写して巧みだ。十五日の小正月女房たちは、加代を焚いた薪を持って、お互いに隙あらば、尻を打つ。そこには新しく、祝いの中心に居る姫の基へ、通い始めた“婿殿”が、宮中へ参内する準備をしている。 通い婚なので男は姫君のところに前夜、やってきてお泊まり。ふざけて駆け回り始めた女房たちは、間違ったふりをして婿殿の尻を叩く。興にのって姫君の尻も叩いて、前夜のことを思い起こさせ、頬を赤らめるのをみて、笑いあうのだ。宮中のような場所でも、「今日は皆乱れて、かしこまりなし(遠慮無い)」とかかれている。 ハナからこれだ。注意深く読んでいくと、多くの段(章と言うべきか)に、ほのかな“色気”が忍ばせてある。「胸のどきどきするもの」と題する章には、こんな表現がある。 「髪を洗い、化粧して,香ばしゅう染みたる衣など着たる。ことに見る人なきところでも、心のうちは,なほいとをかし。待つ人などのある夜、雨の音、風の吹き揺るがすも、ふと驚かる。 お洒落して男を待つ夜の心境が描かれている。雨の音、風の吹き抜ける時の揺れ動く気配にも、胸が騒ぐ。清少納言って、これほど純なのかなー。 ◆幻滅の男 文章の読み方に、上品も下品も無いだろうが、上品な解釈や下品な読み取り方はあるだろうねー。残暑の朝、女の家から”家路を急ぐ”男が居た。板の間に薄縁を敷き、女が薄物を引っ被り寝ている。几帳(ついたて)は外から見えないように立てるべきなのに奥へ押しやってある。役にたたない。外から丸見えないように立てるものだが「奥が気になっていたようだ」とある。そうですか。 清少納言はその女の恋人が帰ってて間もないと推測する。どんな男か気になるし,寝ている女の風情もしどけない-、と書いている。通い婚の実態が、上品に綴られている。下品に読もうと構えれば、それなりに浮かび上がるな。古典・コテンとはこういう読み方かな。 暁の別れの美学、と題する六〇段も面白い。男は暁の別れ際に生き様が分かるのだと書く。 「もう明るくなりますよ」 帰る時が来たことを告げられても男は起き上がらず、袴も着けようとしない。前夜の睦言を耳元で囁いたりして、やっと帯などを結ぶ。ようやく烏帽子の紐などを結び、昨夜散らかしたままの、扇や畳紙などを探し,やっと見つけて扇を使い、懐紙を突っ込む。 「それじゃ帰るか」 身支度もそこそこ。別れの言葉も無く出て行く。昨夜の甘い夢も冷めますよ。 こんなことも書き連ねている。拾い始めるとキリが無い。教科書的な部分も沢山あるが、貴族社会で普通の生活を送っていると,やることは決まっちゃうのかな?100段を過ぎる頃から、日常の描写は生々しさが薄れ、しっぽりとした情緒的な文が多くなる。仕えていた藤原定子が亡くなると宮廷での力は衰え、隠居状態二なる。いくつかの解説や話題の中では「落ちぶれた生活」とまで表現されるが、清少納言、老いたりと言えども意気衰えず。こんなエピソードが、古事談に残されている。 ◆貴族のワル餓鬼をドヤス。  ある日清少納言の家の前を牛車に乗った若い殿上人が数人通りかかった。塀が崩れ建物も壊れかかって、かつてお栄華は偲びようもない。 「少納言も落ちぶれたものだなー」 「今はどうしているのかな。噂も聞かない」 そんなことを声高に話し合っていた。古ぼけた蓮台に簾を掛け、外を眺めていた清少納言は、この声に即座に反応した。簾を跳ね上げ、若者を睨んで言った。 「誰だい。下らないことを言っているのは…。死に馬の骨は買わなかったのかえ」 咄嗟に中国お古事を口にした。逸材を集めようとしていた燕の王に対し、王のアドバイザーは進言した。名馬が欲しいなら、まず死に馬の骨を買うように、と進言した古事。若い貴族は仰天した。 「優れたものは骨になっても大切にする。優れた女性は老婆になっても尊敬するもんだよ。そういう心がけがないと、あんた方、偉くはなれないよ」 若者たちは剣幕と博識振りに答えようもなく、牛にムチをくれて、退散した。 落ちぶれてもめげない清少納言の“老婆の一徹”は、若き日の出来事を彷彿とさせる。あの啖呵。抜き身の賊に向かって前を捲り上げて言い放った一言。 「わたしゃ,女だよ。女を斬るのかえ」 老いてますます盛ん。清少納言の面目躍如。 |
 和泉式部  は は 笛を吹き一人行く保昌、盗賊・袴垂は萎縮(月岡芳年) おぼろ月の夜。静まりかえった道を、男が一人、笛を吹きゆっくりと歩いて行く。さりげない衣装だが、一目で高級品と分かる。 「ワシもそろそろ冬物が欲しい。前を往く奴の着物をを引っぺがそう」 袴垂は一人うなずいて距離を縮めた。と。恐ろしい気配。何だ、と思ったが、近づこうとする度に奇妙な“圧力”が袴垂を襲う。繰り返し接近を試みるが近づけない。業を煮やした袴垂は大声を上げて突進。 「ヤロ、このー!」 男はゆっくりと振り返った。瞬時に倒れていたのは袴垂。意地になってさらに何度か飛びかかろうとしたが、その都度、吹き飛んだり,なにもせずにペタンと這いつくばっていたり…。繰り返した末に笛の男が声を発した。 「誰だ」 「袴垂です」 普通はこんな時に名乗らないだろう。慌てた。大盗賊はガラにも無く、思わず名乗っていた。 「聞いた名だ。ついて来い」 訳も分からず袴垂は男の後に従い、屋敷まで行った。問われて袴垂は、つきまとった理由を話すと男は綿入れの着物を渡し「ものが欲しかったら、この屋敷に来い。つきまとって怪我でもしないようにな」と言った。凄い貫禄に袴垂は魔物を見るようで、ただただ這いつくばって頭を下げるばかりだった。   この男だ。短歌の名手、浮かれ女で知られた和泉式部、二人目の結婚相手は…。しかも、結婚の条件は、天使のお住まい、紫宸殿の庭に生えるさくらの「枝を手折って来たら…」というもの。豪勇の保昌はやりましたねー。警備陣の矢を交わしながら、見事と言って良いのかどうか、とにかく花を付けた桜の枝を手折り、和泉に渡したと言う話が伝わっている。 他にも凄まじい相手とのつきあいも知られる。四天王・頼光の兄弟たち3人。赴任先の常陸、甲斐へ盛んに誘われたと系図には書かれている。遠くまでついていくことはしなかったけれど…。 和泉式部には橘道貞という主人がいた。初婚相手だった。仲の良い夫婦だったが、道貞が地方へ赴任し, 密かに女を囲っていたことが判明てから和泉の乱行が始まったようだ。赴任先の女は正妻としてもいた。怒るのも現代ならば当然だが、時は平安。しかし、和泉は我慢ならなかったようだ。それからだ、後乱行が始まるのは…。 和泉式部は冷泉天皇の子供で三条天皇の弟、為尊親王(ためたかしんのう)と深い仲になっていきます。しかし、為尊親王は早世します。和歌で心情や周囲の人々と交流する様子を描いた「和泉式部日記」は為尊親王が亡くなってすぐに始められていますが、なんとこの日記に登場する男性は為尊親王の弟、敦道親王なのです。 「和泉は情人の為尊親王のお薨(かく)れになった…」で始まる和泉式部日記で、和泉が次の恋人と同衾するまでの展開は、速い、速い。翌年の春、四月。和泉は想い出に浸り、涙にくれていた。その時、為尊親王に仕えていた童侍が現れた。弟君のそつの宮(敦道親王)に仕えているという。 花が沢山咲いている庭先。和泉はそれを手折り 「この花をそつの宮様に差し上げてね。どう思し召すかをうかがってきて下さいな」 「花橘の香を嗅げば昔の人の袖の香ぞする、と言うようなお返事を頂いて参りましょう」 使いの童侍は分かったようなことを言って去った。 和泉は思った。宮様はお若いが浮気な方という名も取っておいでにならないから、自分が歌でご交際をはじめても迷惑なことはどこからも起こってこないだろう、と。 和泉の歌 かをる香によそふるよりは郭公(ほととぎす)聞かばや同じ声やしたると 宮様は童侍から橘の花と歌を受け取った。宮はすぐに歌を書いた。 同じ枝に啼きつつ居りし郭公(ほととぎす)声は変わらぬものと知らなん この歌が始まりだった。みやは童侍に返歌を和泉に届けさせるとき「このことは秘密にしておけ。軽はずみな男のように世間の人から誤解されるから」と念を押した。頻繁な歌の遣り取り。わかりきったことだが、宮は和泉の家へ忍んで行くことになる。和泉は今日だけはお話を伺おうという気持ちになった。 とまあこういう段取りですな。昔、昔の男女の逢瀬は貴族社会では、男が女の家に通うのが、当然のことであっても、言ってみれば兄の情婦を弟が情婦にしようというのは、幾ら厚顔でも気になるところがあるんだなー。 訪れて来た宮と和泉は蓮台で話を始めるが、宮はあーだ、コーダ、と御託を並べ、結局は部屋へ入り込む。何があったかは言うまでも無い。朝が明けようという別れ際に宮は和泉に囁くのだ。 「当分は絶対に私たちの関係を秘密にしなければならないよ」ダト! 出来上がっちゃったあとも、まあ、良くもこれほどと思うほど、歌の遣り取りが続く。訳しているのが情熱の歌人・与謝野晶子。君死にたもうことなかれ…、と軍部を恐れず高らかに歌い上げた御仁だ。恋の火遊び、恋の遣り取りにはたっぷりのご理解がおありで、いささか食傷気味になるくらい二人の恋の歌の遣り取りは終わらない。 伊勢物語は在原業平の歌行脚だが、和泉式部日記も歌で綴る物語。敦道親王もやはり若くして亡くなり、和泉はがっくり、再起不能かと思うけど、そんなことはありません。 怪盗・袴垂を気合いと貫禄で屈服させた藤原保昌と結婚する快挙。イヤ、怪挙?これは最初に記した。  藤原道長 つきあいの広い和泉は若い男性に扇をプレゼントした。調子に乗った男はその扇を見せびらかして、あたかも自分の夜這いする相手のように自慢していた。本当に一夜を共にしたのかもしれない。そこを最高実力者の藤原道長が通りかかった。 「ちょっと扇を貸せ」と道長。従者から筆を受け取りすらすらと扇に走らせた。 「浮かれ女の扇」 ポイと投げるように返された扇の文字を男に見せられた和泉は、即座に歌を返した。 越えもせむ 越さずもあらむ 逢坂の 関もり(守)ならぬ 人なとがめぞ (越えようが、越えまいが 逢坂の関(男女の出会いの場)は自由でしょう。関守でもない御方におとがめされるいわれは御座いません) さすが道長、さすがが和泉。澄まして頭を下げて歌を渡す和泉に、道長は笑いながら去って行った。貴族社会で歌は身分を超えて評価されるものだった。 こんな和泉を紫式部はお気に召さない。キツーい一言。 「あの子は歌は上手。友達に書く手紙もさえた言葉が散りばめられているわ。だけど悪い癖。浮気女で素行はいけません」 和泉は娘が居た。和泉初婚お相手、道貞との子だった。 小式部内侍と小を付けて母と区別された。彼女にも言い寄る男が多く、歌もまた、冴えていた。子供も産んだが二十代後半で亡くなっている。 以前、古記談を見ていて“これは”と思ったところがあった。空也上人という当時知られた僧と歌の遣り取りを密かにやっていた。上人は当然,和泉式部の行状は承知。歌の才能も聞き知っていたろう。空也上人は歌を送った。 空也上人 極楽は なほき人こそまゐるなれ まがれる事を 永くと留めよ (極楽は真っ直ぐな人が行くところだ。曲がった事はずっと我慢しなさい) 和泉式部(返し) ひじりだに 心にいれてみちびかば まがるまがりも 参り付きなむ (上人が心を込めて導いて下されば 曲がりながらでも ついていきますよ) 上人が何故、和泉に歌を送って、生き方について語ったのか-。”コテン流”に考えると,下心無しとは言えない。浮気女の噂も高い和泉に、曲がった事とは一体何だ?見えますねー。上人の”凡人的一面”が…。 応える和泉もなかなかです。 上人様がその気になられてお導き下されば、それに従い極楽へご一緒できるでしょう。 何じゃ,こりゃ! 深読みのしすぎですか。 |
 紫式部 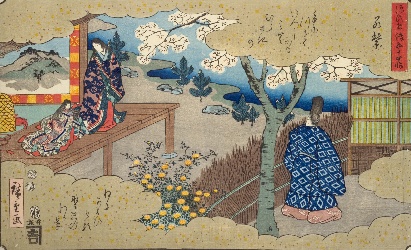 国立国会図書館 文武両道。輝く美男子、しかも管弦・舞踏までこなす-。平安のサッカー、蹴鞠の才にまで恵まれている。こんな男、居るの?それがいるんだよ。 光 源氏。 お話なんだけど、源氏物語の主人公がその人。 清少納言は随筆、和泉式部は短歌、紫式部は恋に明け、恋に暮れた平安貴族の理想の塊を夢に描いて書き下したのか-。希代の色事師?在原業平も詩ならともかく、巧みな貴族社会に生きる“泳法”では光源氏に到底及ばないナー。 紫式部はこういう男を理想としていたのかな。小説の途中には、当然のlこととして山坂はあり、そうなると当たり前のスキャンダルも頭を出しているのだが、巧みに“言いくるめ”ているようだ。「下品なシーンや表現は無いかな」なんてあら探しする専門家?などをみに交わす筆の冴え。  美女が引く手あまたなのはいつの時代でも変わらないが、紫式部は上流貴族の恋門語り「源氏物語」を執筆していながら、浮気女は大嫌い。自らはお堅い、生真面目な性格だったようだ。和泉式部は両手指に有り余る?ほどの男どもとの交流が書かれていて、本人自身も“記憶の外”へと追いやった男は多かったようだ。一部では「藤原道長が夜這いした」の話さえある。 紫式部は二十歳半ばで結婚(藤原宣孝)一子・賢子を生んでいるが、僅か三年で夫は亡くなっている。だからと言って浮気女に転身してはいない。手堅い生き方なのは、紫式部日記で明白。手元には情寝つん詩人・与謝野晶子訳の紫式部日記・和泉式部日記があるが、紫式部の“癖”なのか,平安朝文学の流れなのか、自らの恋?ンい関係するのかな、と思うところは、短歌の遣り取りになっている。 与謝野さんの現代文訳は明治の言葉遣いなのだろう、現代文としてはちょっと読みにくいところもあるが、歌人なので詩は日常のものなのという意識なのだろう、訳してなくて、現物そのものだ。平文の部分にも,もちろん”それらしい”表現はあるが、自らが関係する出来事ではなく、他人事として表現しているので「よしよし。紫さんも人の子」などとにやついても,肩すかしを食らうばかりだ。さすが自ら作り上げた光源氏を手玉にとって、読む人を引きずり回す筆力を持ったお人だワイ。 夫・宣孝が亡くなって以降、結婚はしていない。そんな紫は、あまり書かれてはいないが、相当の美人だった。従って言い寄る男は絶えること無し。 そんななかで、歌人としても知られた藤原公任が紫式部と恋仲だった-、の話も広がっていた。この男は上級貴族の中でも優れた血統を持っている。母親、妻共に天皇家に連なる。父親は天皇の側近、彼自身も多才で単価のほかにも漢詩、音楽も知られた上手なので、貴族社会でもエリート中のエリートというべきだった。   紫式部は道長の娘、彰子の女房として教育係的な仕事をしていた。公任も宮中勤務。出会う機会は多い。ただ、決め手となるような証拠は幾つかの資料にも記されてはいない。色事とはそういうものかもしれないし、それほど周囲に気を配っていたのかも知れない。 しかし、新訳紫式部日記(与謝野晶子訳)には、酔った公任が紫式部に“親しくなければ”ないと思える冗談も記されている。その一部を写し書きする。 「ええと、この辺りにおいでですか、若紫は」 といって御簾の中を窺っていた。自分は源氏物語のなかに賞めて書いた女性のいずれにも当たっていないと謙虚な心で思っている。ましてこの辺に若紫の夫人をもって自任している作者がいるわけはないと自分は苦笑しながら聞いていた。 酔っているとはいえ、源氏物語中の人物“若紫”を探す公任を苦笑しながら見ているあたりは、相当の親しさが無ければ、通じるものではあるまい。さらに二人の関係をほのめかす記述を参照として添付する。 場面は叡山の寺で仏事が行われ、そのあと夜まで大勢が広い庭で遊び、おぼろ月の中若い男たちは酒を飲み、賑やかに遊んでいた。女たちもその中に加わって楽しんでいたが、紫式部は御簾の中にいた。その時、ふらりと道長が現れ置いてあった源氏物語を手にとって見ながら冗談を言って紫たちを笑わせた。そして置いてあった紙を取り上げ歌をすらすらと書いた。 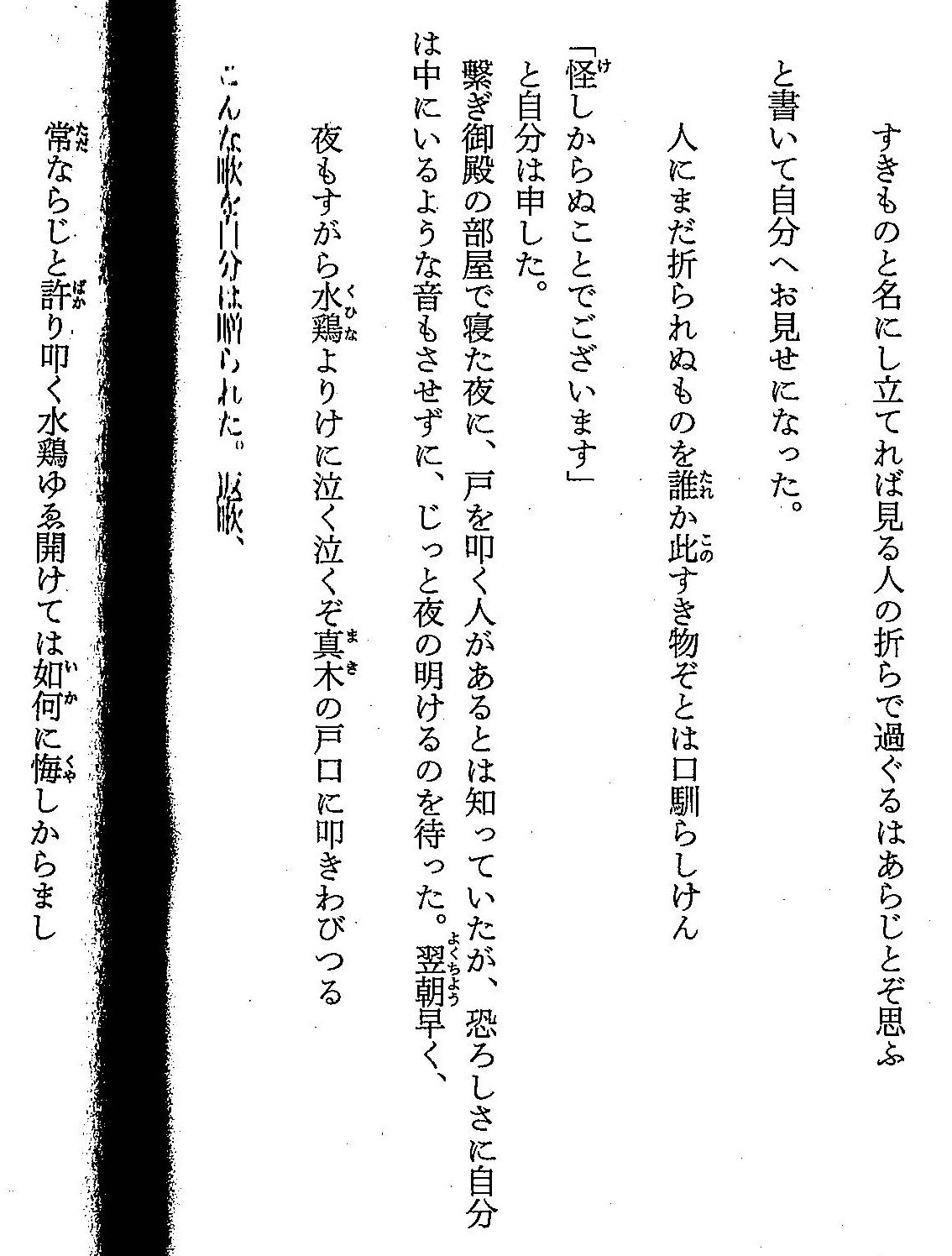 前の「すきものと…」の部分は深読みしたくなる。好き者と評判が立っているのに、折らず(さてどう訳す?)に通り過ぎるのは,無いよな…、と書いて紫に見せる。これ自体、相当深い関係か、冗談が通じるまでになっていないと、普通はあり得ない。 紫の返歌というのか、応えて言葉にしたのか、また面白い。 「人が手を付けていないのに、好き者というのはどういうことですか」。 「けしからんことでございます」 ウーン。さすが紫式部 上のコピー半ばから左の表現は、目に見えるようだ。寝ていると戸を叩く音。夜中だ。じっと固まって夜明けを待ったと書いてある。夜明け。歌が届く。水鶏(くいな)と言う鳥は,戸を叩くコンコンと言う音をだすという。それに掛けて歌が届けられた。 夜中に戸を叩いたが、沙汰無し。戸口で水鶏のように泣いたぞ-。 返歌 普通じゃないみたいに戸を叩いたようですが、音につられて開けようものなら、きっと悔しい目にあっていたでしょうね。 道長と紫式部は愛人関係には無かった、と言うセンセ方もいるが,ワシャ、この遣り取りで、深い仲じゃ無いとは到底思えないな。  それにしても、藤原家の総帥を深夜戸口に立たせて“コケ”にした、紫式部は自信家だなー。道長は執筆中から源氏物語のファンだったそうで、書き進む度に読み継いでいたとされる。紫を孫の彰子に付け、指導させていたので、親しい関係は却ってばれにくかったのかも知れない。 全く別の話だが、当時の世情をあからさまに書いてあるのは、、後撰和歌集の選者、大中臣能宣(おおなかおみよしのぶ)の話。 ある夜、能宣は女房(妻ではない)と女の部屋で寝ていた。使いが来て主人の皇后に呼ばれていると伝えた。女は「待っててね。眠らないで…」と出て行ったが帰ってこない。呼ばれたのlが皇后だったかどうか怪しい。どうやら別の男と寐て、朝になって帰ってきたようだ。 「夕べは寐られました?起きてましたか」 さすが平安男も怒ったが「眠くはなかったぞ。他の男と寐ていると思うと目は冴えて,寐るどころじゃない」と言う意味の歌を渡した。こういう世の中だった。数人の女の情人となるが、女にもまた数人の情夫がいるという案配。良い時代というか、ふざけた時代というか、貴族社会の話ではあるが…。当時の倫理感は好きなように生きることを良しとしたのだろう。 源氏物語はそんな貴族社会を描いているが、紫式部の巧みな筋書き作りなのか、遠くから眺めるようなところもある。ここでは平安時代の才女・三人の姿のほんの一面を書くことで,時代を感じてもらえればと思う。 |